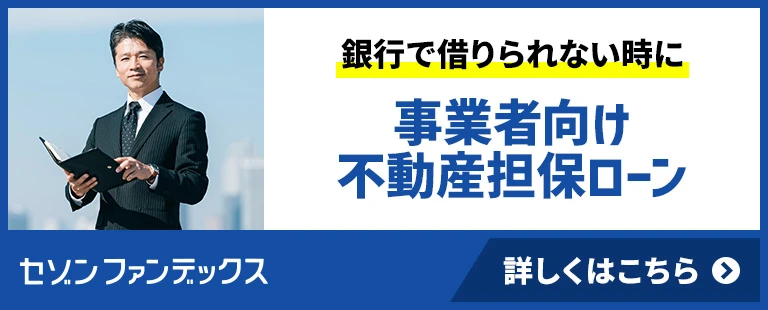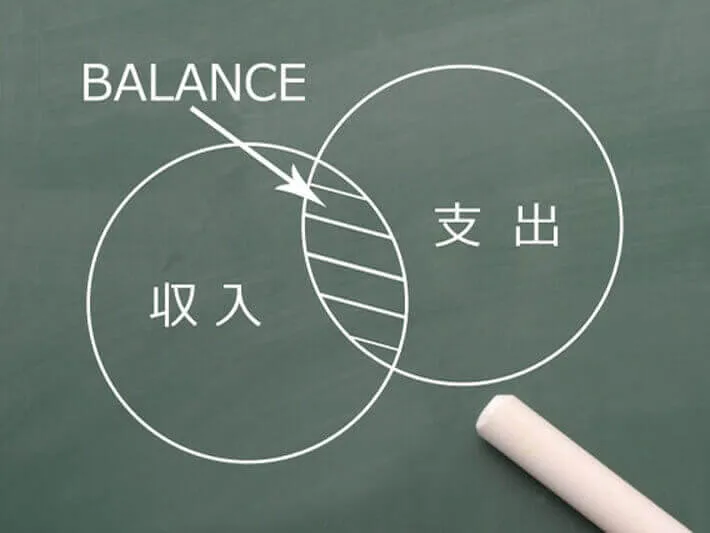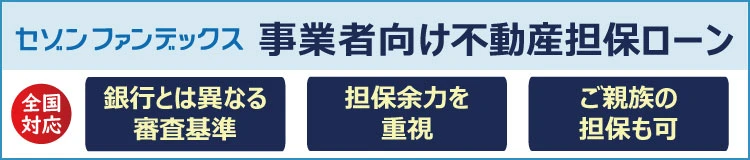更新日
税金滞納で差し押さえ…「生活できない」は本当?守られる財産・今すぐできる対処法を徹底解説

.webp)
| 執筆者氏名 | 「お金のトリセツ」編集部 |
|---|---|
| 所属 | セゾンファンデックス |
| 執筆日 | 2025年09月26日 |
税金滞納による「差し押さえ通知」が届いた瞬間、多くの人が「人生終了」を覚悟してしまいます。「全財産を失うのでは…」「家族や職場にバレたら…」という恐怖に支配され、パニック状態に陥ってしまうのも無理はありません。 しかし、これは大きな誤解です。 実は法律により、生活に最低限必要な財産は確実に守られており、「すべてを失う」ことは決してありません。現金66万円まで、給与の4分の3、生活必需品などは差し押さえ禁止となっているのです。 一方で、放置や無視を続けることこそが最も危険な行動。預金口座の凍結、給与の部分差し押さえ、さらには不動産の公売まで現実となり、本当に生活が困窮してしまいます。 本記事では「税金滞納=絶望」という思い込みを解消し、正しい知識と具体的な対処法をお伝えします。 守られる財産の範囲から緊急時の資金調達方法まで、専門家監修のもと実践的な解決策を詳しく解説。今まさに困っている方が「何をすべきか」「どこに相談すべきか」が明確になります。 重要なのは一人で抱え込まず、すぐに行動を起こすことです。
目次
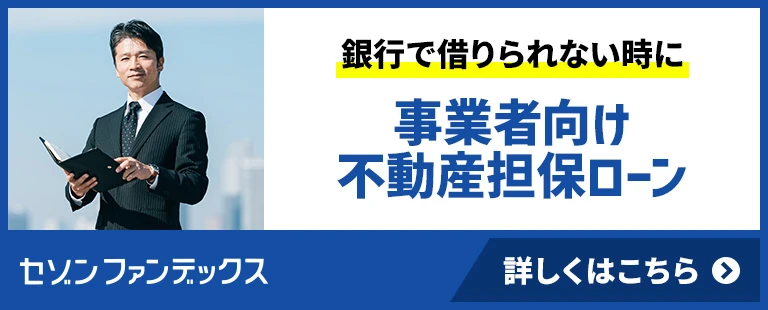
税金滞納で「生活できない」は本当?守られる財産・奪われる財産の現実
税金滞納による差し押さえでも「全財産を失う」とは限りません。まず守られる財産・差し押さえ対象になる財産の違いを知っておきましょう。
差し押さえでも"最低限の生活"は法律で守られる
差し押さえを受けても、生活再建が不可能になるほど全財産を奪われることはありません。 これは「国税徴収法」(第75条、第76条)で、生活に不可欠な財産の差し押さえが禁止されているためです。
<差し押さえ"禁止"の主な財産>
- 現金:66万円まで(約2ヶ月分の生活費相当)は手元に残せる
- 給与:4分の3、または手取り33万円までは差し押さえ不可
- 年金:国民年金は全額保護、厚生年金は4分の3(または33万円まで)保護
- 生活必需品(衣類・寝具・家具・食料・燃料など)
- 生計や仕事に不可欠な道具・実印など ※(例)手取り20万円の給与なら、差し押さえは5万円まで/15万円は守られる
差し押さえ"対象"となる主な財産
- 預金(銀行口座):全額差し押さえ可
- 給与の一部(上限あり/上記参照)
- 不動産(自宅・土地・事業所等)
- 自動車、貴金属、骨董品など高価資産
- 有価証券(株式・投資信託)
- 事業収入・売掛金 など
【早見表】差し押さえOK/NG財産
| 財産種類 | 差し押さえの可否 | 備考 |
| 現金 | ×(66万円まで守られる) | 超過分は差し押さえ可能 |
| 銀行預金 | ○ | 全額が対象 |
| 給与 | ×(4分の3・33万円まで) | 手取りの4分の1のみ対象 |
| 生活必需品 | × | 法律で明確に差し押さえ禁止 |
| 持ち家・土地 | ○ | 公売にかけられる |
| 賃貸住宅 | × | 家賃滞納時以外は対象外 |
| 年金 | ×(国民年金は全額保護、厚生年金は4分の3保護) | 国民年金は全額差し押さえ禁止、厚生年金は4分の1のみ対象(国税徴収法第76条) |
差し押さえが「本当に生活に及ぼす影響」とは?
最低限の現金・給与・家財は守られるので、「即日生活できなくなる」ことはありません。しかし預金口座がゼロ、給与差し押さえが続く、不動産の公売などが現実化すれば、家計や事業に深刻な影響を与えることになります。
また、会社や家族への通知も発生(給与差し押さえ時など)するため、精神的な負担も大きくなります。ただし、相談・交渉・分納による差し押さえの回避・解除も十分可能です。
差し押さえの具体的な流れ——いつ何が起きる?

差し押さえが実際に始まるまでの流れを、時系列で解説します。「いつ・どんな通知が来るのか」「どこから手が付けられるのか」を理解しておきましょう。
【STEP 1】納付期限を1日でも過ぎると「滞納」状態に
- 納期限超過→自動的に延滞税発生
【STEP 2】督促状・催告書の送付(約20〜50日以内)
- 「督促状」が自宅に届く
- これを無視すると、より強い「催告書」「差押予告通知」などが届く
【STEP 3】財産調査・勤務先調査
- 税務署・自治体による預金・給与・不動産などの調査
- 会社へも在籍確認等が行われる場合あり
【STEP 4】差し押さえ実行(最短で2〜3ヶ月〜)
- 何度も無視・放置した場合、予告なく実施されることも
- 差し押さえられた財産は、公売や強制換価により滞納税へ充当
差し押さえは「ある日突然」やってくる?
督促状・催告書を無視し続けると、本当に"ある日突然"自宅や職場で差し押さえが行われる場合があります。だからこそ、「督促状が来たら即・相談」が鉄則です。
今すぐできる現実的な対処法と相談先
差し押さえを回避・解除するには、すぐに取れる行動があります。やってはいけないNG行動や、相談できる窓口についても解説します。
絶対NGな行動
- 督促状・通知を「無視」「放置」
- 税務署や役所からの電話・訪問を無視
- 嘘の申告や無断転居 →これらは"即差し押さえ"や最悪の事態を招きます
まずやるべきこと
(1)税務署・自治体に「すぐ相談」
- 払える分だけでもすぐ支払い意思を示す(分納・猶予交渉が可能)
- 早めに行動することで分割払い・納税猶予が認められやすくなる
(2)分割納付や納税猶予を申請
- 経済事情を説明すれば、無理のない返済計画が認められるケースが多い
(3)生活保護・公的福祉を活用
- 本当に支払えない場合は、生活保護の相談も選択肢
- 生活保護世帯は多くの税金が免除、差し押さえも回避可能
(4)弁護士・税理士・法テラスなど無料相談も積極活用
- 税金だけでなく、借金・家計・法的問題もまとめてアドバイス可能
「家計がもたない」場合は迷わず資金調達も検討
- 自宅や土地など不動産があれば、不動産担保ローンで資金調達し、滞納分の支払いも可能
- 金利・返済計画は要確認だが、「最悪の強制売却」を回避できることも
【よくあるQ&A】差し押さえで困ったときどうする?
「生活できなくなる?」「家族や会社にバレる?」「差し押さえ後に取り戻せる?」など、よくある疑問に専門家視点で回答します。
Q1. 差し押さえで「本当に生活できない」状態になる?
→ 最低限の生活(66万円の現金、給与4分の3、家財)は守られるが、口座ゼロや給与差し押さえが長期化すれば家計は大きく圧迫。家族や職場にも知られるリスクあり。
Q2. 差し押さえられた財産は取り戻せる?
→ 換価前(売却前)に滞納税を全額納付できれば、差し押さえ解除・返還も可能。 換価後は基本的に戻らないが、余剰分は返還される。
Q3. 会社や家族に知られる?
→ 給与差し押さえ時は勤務先に通知が行き、家族にも自宅宛に郵送されるため、高確率で知られる。
Q4. 賃貸住まいなら退去になる?
→ 家賃を滞納しない限り、税金滞納を理由に住まいを追い出されることは基本的にありません。
Q5. 他の借金も苦しい場合は?
→ 債務整理(自己破産・個人再生)も選択肢。ただし税金の免責はできないが、他の借金負担が減ることで税金の支払い余力が増す。
【実際の体験談】差し押さえを乗り越えた事例
差し押さえに直面した方が、どのように解決したのか——実際の体験談から、今すぐ役立つヒントを紹介します。
給与差し押さえ通知が会社に届いたケース
「住民税を滞納していたところ、ある日突然会社の経理部から呼び出されました。市役所から給与差し押さえの通知が届いたとのことで、恥ずかしくて職場に居づらくなってしまいました。しかし、すぐに市役所の納税課に相談に行き、家計の状況を正直に説明したところ、月2万円の分割納付で合意してもらえました。差し押さえも解除され、会社の上司にも事情を話して理解してもらえたので、今では安心して働けています。」
銀行口座が差し押さえられたケース
「国民健康保険料を半年滞納していたら、ある朝銀行に行くと口座残高がゼロになっていました。パニックになりましたが、役所に問い合わせると、現金は66万円まで保障されると教えてもらいました。実際に手元には生活費が残っていたので、まずは落ち着いて相談することができました。その後、月1万円の分割払いで合意し、今は順調に支払いを続けています。最初は絶望的に感じましたが、きちんと対応すれば解決できることを実感しました。」
「本当に困ったとき」の資金調達と再建策——最悪でも道はある

不動産など資産があれば、「不動産担保ローン」で資金調達が可能です。銀行融資が難しい状況でも、ノンバンクの事業者向けローンは柔軟に対応してくれます。ただし、金利・返済計画はしっかり比較検討し、納税後の生活再建も重視することが大切です。
特に事業を営んでいる方の場合、事業継続に不可欠な資金が不足すると深刻な状況に陥りがちです。そのような場合は、「事業計画・返済計画」を重視するノンバンク融資や不動産担保ローンの活用も選択肢の一つです。銀行融資が難しい場合でも、柔軟な審査で納税資金・運転資金の調達が可能なケースがあります。
まとめ「一人で抱え込まず、今すぐ行動を」
税金滞納で「差し押さえ」を受けても、最低限の生活は守られます。 ただし、放置すれば給与・預金・家・車など大切な財産を失うリスクも。
- 督促状が来たら"すぐ相談・すぐ対応"が最優先
- 「払えない…」と一人で抱え込まず、必ず税務署や専門家に相談を
- どうしても資金調達が難しい場合は、「不動産担保ローン」など資産活用も検討可能
早めの行動が「生活・家族・事業」を守るカギです。