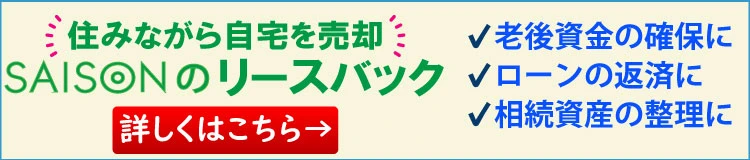更新日
80代の貯金中央値は600万円|老後資金の現実と不足時の対策法
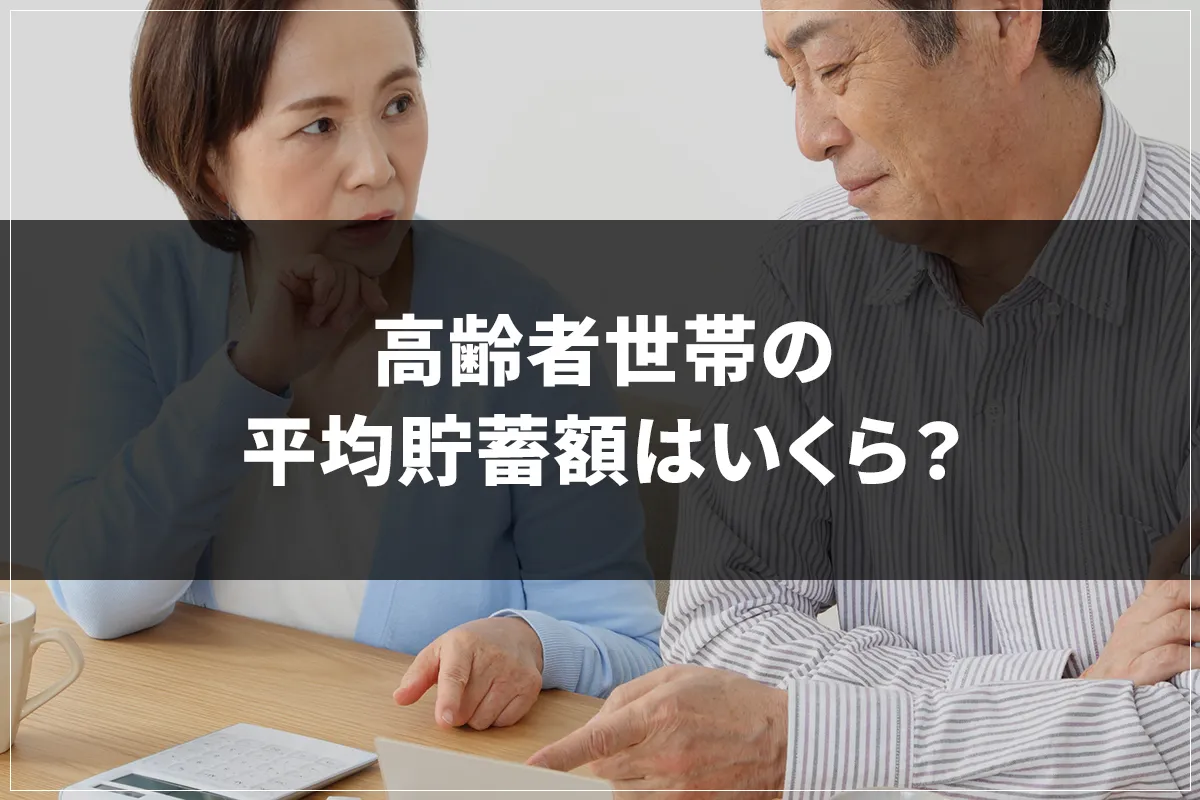
「80代になったら貯金はどのくらいあれば安心なの?」「みんなどれくらい持っているんだろう?」そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。 2024年に発表されたデータによると、80代の貯金中央値は約600万円。しかし、この数字だけを見て一喜一憂する必要はありません。なぜなら、本当に必要な老後資金は、あなたの生活スタイルや家族構成、住まいの状況によって大きく異なるからです。 この記事では、80代の貯金事情を公的データで詳しく解説するとともに、「貯金が足りない場合の対処法」「自宅を活用した資金調達方法」といった具体的な解決策もご紹介します。 統計の数字に惑わされず、あなたらしい安心できる老後生活を実現するためのヒントを見つけてください。
目次
- 80代の貯金事情を徹底解析――公的データで見る現実の数字
- 貯金が少なくても大丈夫!80代の2割は「貯蓄ゼロ」でも生活している現実
- 老後の生活費の現実――データで見る「本当に必要な金額」
- 現実を知ろう――80代夫婦の「老後資金不足額」を具体的にシミュレーション
- 統計の数字に一喜一憂しなくていい――あなたに必要な老後資金は「あなただけのもの」
- 貯金が足りない時の現実的な老後資金の備え方――あきらめる前に試したい3つのアプローチ
- 自宅を活用した資金調達――今注目の「リースバック」という賢い選択
- セゾンのリースバック──「資金調達+住み続ける」を両立
- 「必要なときに少しだけ」ならかんたん安心カードローン!
- まとめ──「中央値」は世間の目安、自分に必要な資金を現実的に備えよう
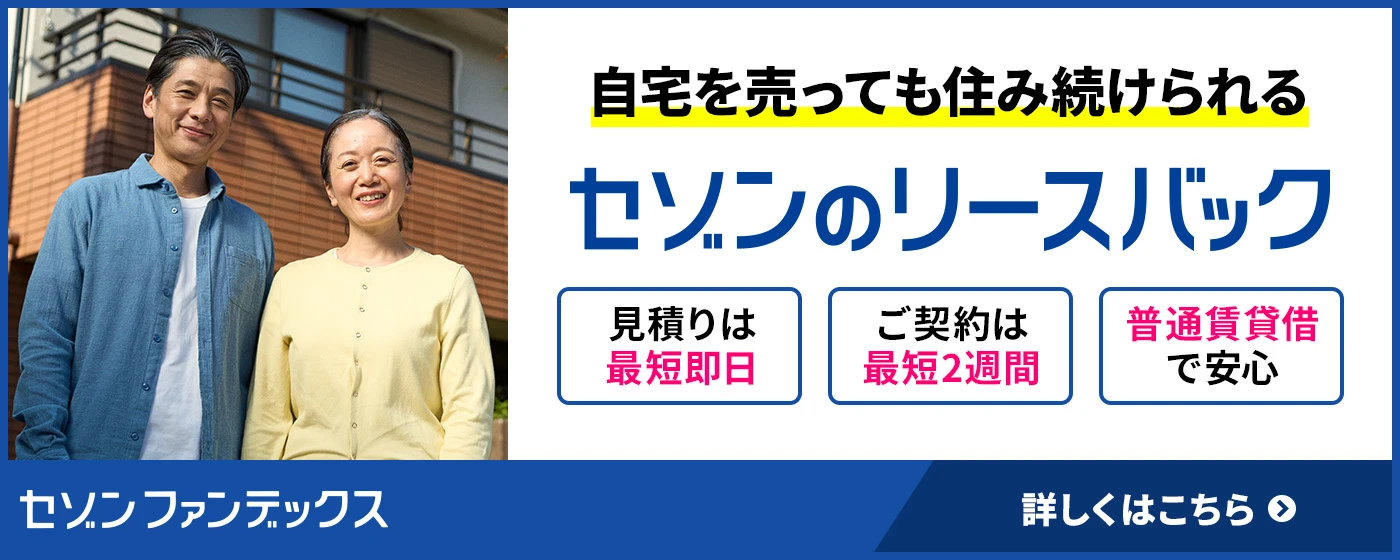
80代の貯金事情を徹底解析――公的データで見る現実の数字
「80代の人たちは、実際どのくらい貯金を持っているの?」この疑問に、公的データでお答えします。
80代の貯金中央値は約600万円
金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査]」(2024年発表)によると、80代単身世帯の金融資産保有額の中央値は約600万円となっています。
年代別で見ると右肩下がりの傾向
年齢が上がるにつれて貯金額は減少していく傾向が見られます。
- 60代:約800万円
- 70代:約700万円
- 80代:約600万円
この傾向は、退職後に貯蓄を生活費として取り崩していく現実を反映しています。
中央値と平均値の大きな違いに注目
同調査から、80代の金融資産についての中央値と平均値が大きく違うことも確認できます。
- 中央値:約600万円
- 平均値:約1,600万円
平均値が中央値の約2.7倍も高くなっているのは、一部の高額資産保有者が全体の平均を大きく押し上げているためです。つまり、多くの80代の方の実感に近いのは「600万円」の方だということです。
この600万円という数字をどう解釈するか
600万円という中央値は、
- 全国の80代を貯金額順に並べた時の「真ん中の人」の金額
- 半数の方がこれより多く、半数の方がこれより少ない
- あくまで「参考値」であり、あなたに必要な金額とは別物
しかし重要なのは、この数字と自分を比較することではなく、あなた自身の生活に本当に必要な資金を把握することです。
貯金が少なくても大丈夫!80代の2割は「貯蓄ゼロ」でも生活している現実
「80代の貯金中央値が600万円」と聞くと、それより少ない貯金の方は不安になるかもしれません。しかし、実はもっと厳しい状況の方も決して珍しくないのです。
80代の約2割が「金融資産ゼロ」という現実
金融広報中央委員会の同調査によると、80代単身世帯のうち約2割が「金融資産ゼロ」と回答しています。つまり、5人に1人が貯金なしで老後生活を送っているということです。
「貯金ゼロ」でも生活できている理由
では、なぜ貯金がなくても生活が成り立っているのでしょうか?
- 年金収入が生活費をカバー:質素な生活により年金の範囲内で生活
- 持ち家のメリット:住居費がかからないため支出を大幅に削減
- 家族からのサポート:子どもや親族からの経済的・生活面での支援
- 公的制度の活用:医療費助成や介護サービスなどを適切に利用
- 必要に応じた働き方:体力に合わせた軽作業やパートタイム
あなたは決して一人じゃない
もしあなたの貯金額が中央値の600万円より少なくても、それは「異常」なことではありません。多くの同世代の方が同じような状況で、それぞれ工夫しながら充実した老後生活を送っています。
大切なのは「今できること」に目を向けること
貯金額の多い少ないよりも重要なのは…
- 今の収入と支出のバランスを把握する
- 利用できる制度やサービスを知る
- 持っている資産(家、経験、人脈など)を活かす
- 無理のない範囲で生活を楽しむ
統計の数字に惑わされず、あなたらしい老後生活を実現する方法はきっと見つかります。
老後の生活費の現実――データで見る「本当に必要な金額」
老後資金を考える前に、まずは「実際にいくら必要なのか」を把握しましょう。公的機関の最新調査から、リアルな数字をご紹介します。
【夫婦2人世帯の生活費】
生命保険文化センター「生活保障に関する調査(2022年)」によると
最低限の生活レベル
- 月額:23.2万円
- 年額:約278万円
ゆとりある生活レベル
- 月額:38万円(最低限+14.8万円)
- 年額:約456万円
年金収入との現実的なギャップ
一方、年金収入の現実は厳しいものがあります。
モデル年金額(夫婦2人世帯)
- 月額:約22万円
- 年額:約264万円
- 出典:厚生労働省「令和5年度 厚生年金・国民年金事業の概況」
毎月の不足額を計算すると
- 最低限の生活:23.2万円 - 22万円 = 月1.2万円不足
- ゆとりある生活:38万円 - 22万円 = 月16万円不足
年間・10年間で見ると深刻な金額に
- 年間不足額:14.4万円
- 10年間:144万円
- 年間不足額:192万円
- 10年間:1,920万円
多くの高齢者世帯が年金だけでは生活できず、貯蓄を取り崩しながら暮らしているのが現実です。だからこそ、現役世代のうちからの備えや、シニア世代になってからの資産活用が重要になってくるのです。
重要なのは、この現実を踏まえて「自分たちはどのレベルの生活を目指すのか」「そのためにはどんな準備が必要か」を具体的に考えることです。
現実を知ろう――80代夫婦の「老後資金不足額」を具体的にシミュレーション
「老後資金が不足する」とよく言われますが、実際にはどのくらい足りないのでしょうか?モデルケースで具体的に計算してみましょう。
【標準的な80代夫婦世帯のケース】
収入面
- 厚生年金(夫婦合計):月22万円
- 年間収入:264万円
支出面
- 月間生活費:30万円(※比較的堅実な水準)
- 年間支出:360万円
年間の収支
- 264万円(収入)- 360万円(支出)= 年96万円の赤字
10年間で必要な貯蓄取り崩し額 96万円 × 10年 = 960万円
さらに考慮すべき追加費用
上記はあくまで「日常生活費」のみ。実際にはこれに加えて:
- 医療・介護費用:年間50万~100万円程度
- 住宅修繕・設備更新:10年で200万~300万円
- 冠婚葬祭・突発的支出:年間20万~30万円
これらを含めると、10年間で1,200万~1,500万円程度の備えが必要という計算になります。
80代の貯金中央値600万円では明らかに不足
この現実を見ると、統計上の中央値600万円では到底足りないことが分かります。だからこそ、多くのシニア世代が
- 支出の見直しで赤字幅を縮小
- 働ける範囲での収入確保
- 自宅などの資産活用
といった対策を組み合わせて、老後生活を成り立たせているのです。
重要なのは、この現実を「絶望的」と捉えるのではなく、「対策すべき課題」として前向きに取り組むことです。
統計の数字に一喜一憂しなくていい――あなたに必要な老後資金は「あなただけのもの」
「80代の貯金中央値は600万円」と聞いて、自分の貯金額と比較して落ち込んだり安心したりしていませんか?実は、この統計的な数字は、あなたの老後生活の充実度を決める指標ではありません。
同じ80代でも、必要な老後資金は人によって大きく異なります。例えば…
- Aさん(持ち家・年金月20万円):住居費がかからず、質素な生活で月15万円あれば十分
- Bさん(賃貸・年金月15万円):家賃8万円に加え、持病の治療費で月25万円が必要
- Cさん(持ち家・年金月25万円):趣味の旅行や孫への支援で月35万円を希望
この3人の「必要貯金額」は数百万円単位で変わってきます。
- 住まいの状況:持ち家か賃貸かで毎月数万円の差が生まれます
- 健康状態と医療費:持病や介護の必要性によって大きく左右されます
- 理想とする生活水準:必要最低限で良いのか、ゆとりを求めるのか
「自分軸」で老後資金を考えよう
大切なのは、世間の平均ではなく「あなたの現実」を把握すること。まずは以下を整理してみてください:
- 現在の月間支出額
- 受給予定の年金額
- 住まいや健康面で想定される変化
- 本当に大切にしたい生活の要素
この「あなただけの老後資金計画」こそが、統計の数字よりもはるかに価値のある指標となります。
貯金が足りない時の現実的な老後資金の備え方――あきらめる前に試したい3つのアプローチ
80代の貯金中央値と比べて「足りない」と感じても、まだできることはたくさんあります。多くのシニア世代が実践している、現実的で効果的な方法をご紹介します。
1. 支出の最適化で家計を改善
固定費の見直しから始める
- 携帯電話・インターネット料金の格安プランへの変更
- 不要な保険やサブスクリプションサービスの整理
- 電気・ガス会社の見直しで光熱費削減
公的制度・自治体サービスの活用
- 医療費の高額療養費制度や後期高齢者医療制度
- 自治体の高齢者向け割引サービス(交通費、施設利用料など)
- 介護保険サービスの適切な利用
2. 無理のない範囲で収入を増やす
現在、65歳以上の就業者は約914万人と過去最多を記録しており、「働くシニア」は珍しくありません(出典:総務省「統計トピックスNo.142 統計からみた我が国の高齢者-『敬老の日』にちなんで-」(2024年9月公表))。
人気の働き方
- シルバー人材センターでの軽作業や事務補助
- 経験を活かしたコンサルティングや指導業務
- 在宅でできるデータ入力や電話対応
- 趣味を活かした手工芸品販売やオンライン講師
3. 資産を賢く活用・運用する
- 安全性重視の資産運用:高齢世帯の約2割が国債・債券・投資信託などを活用し、「リスクを抑えながら資産を守り増やす」運用を実践しています。
- 自宅という最大の資産を活用:持ち家をお持ちの方なら、リースバックで住み続けながら資金調達する方法もあります。詳しくは後述します。
- 重要なのは「組み合わせ」:これらの方法は単独ではなく、あなたの状況に合わせて組み合わせることで、より大きな効果を期待できます。
自宅を活用した資金調達――今注目の「リースバック」という賢い選択
老後資金が不足していても、持ち家があれば新たな解決策があります。それがリースバックです。
リースバックとは?
リースバックは、あなたの自宅を専門会社に売却してまとまった資金を得ながら、売却後は家賃を支払って同じ家に住み続けられる取引手法です。
こんな悩みを解決できます
- 「老後資金は足りないけれど、住み慣れた家を離れたくない」
- 「引っ越しの手間や費用をかけたくない」
- 「固定資産税や修繕費の負担が重い」
- 「将来の相続で家族に迷惑をかけたくない」
リースバックの3つのメリット
- 住環境を変えずに資金確保:ご近所付き合いや生活リズムはそのまま
- 所有者負担からの解放:固定資産税や火災保険などが不要に
- 相続問題の解決:不動産を現金化することで、相続トラブルを未然に防止
近年、このリースバックを選択するシニア世代が急速に増えており、老後の新しいライフスタイルとして定着しつつあります(出典:国土交通省「不動産取引に係る新たなサービス形態について」(2025年2月))。ただし、家賃負担や契約条件も含め、ご家族や専門家とじっくり相談した上で検討することが大切です。あなたの自宅も、住み続けながら老後資金に変えられる貴重な資産かもしれません。
セゾンのリースバック──「資金調達+住み続ける」を両立
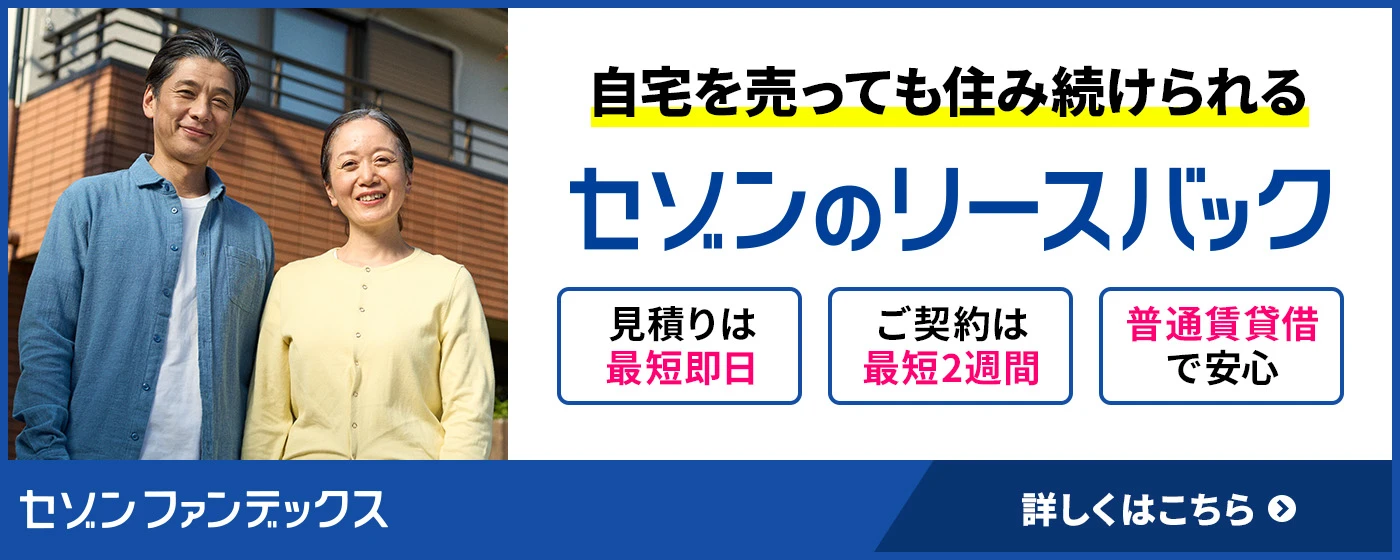
老後資金の確保と住まいの安心を両立したい方に注目されているのが、セゾンのリースバックです。
取引の流れと特徴
- 自宅の売却:お客様の自宅をセゾンファンデックスが買い取ります
- 賃貸契約:売却と同時に賃貸契約を結び、そのまま住み続けることができます
- 負担軽減:固定資産税などの所有者負担から解放されます
こんな方におすすめ
- まとまった老後資金が必要だが、引っ越しは避けたい
- 固定資産税を軽くしたい
- 相続で家族に迷惑をかけたくない
- 将来的に買い戻しも検討したい
住み慣れた環境を変えることなく、資金面の不安を解消できる新しい選択肢として、多くのシニア世代に選ばれています。具体的な条件や手続きについては、まず無料相談でお気軽にご相談ください。
「必要なときに少しだけ」ならかんたん安心カードローン!
まとまった資金ではなく、「必要なときに少しだけ借りたい」という方にはカードローンという方法もあります。
セゾンファンデックスのかんたん安心カードローンでは、80歳までの方もお申込みいただけ、お急ぎの方にはお申込み当日のご融資も可能(※)です。
※平日12時までにお申込みで当日13時までにお手続き完了の場合、15時までにお振込み
必要な分だけ借り入れ可能で、使い道も自由!
老後資金や生活費の一時的な補填などに、ぜひご活用ください。
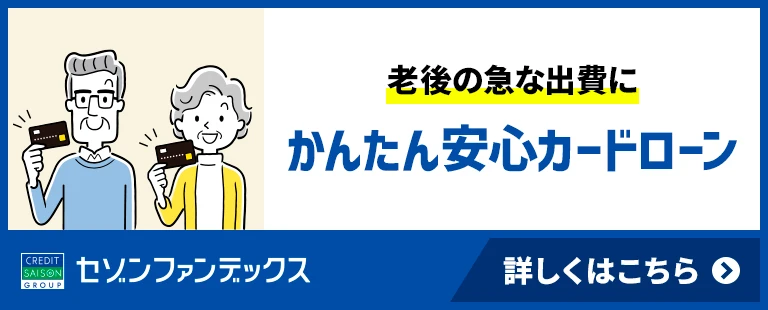
まとめ──「中央値」は世間の目安、自分に必要な資金を現実的に備えよう
80代の貯金中央値600万円という数字は、あくまで統計上の目安に過ぎません。重要なのは、この数字と自分を比較することではなく、あなた自身の生活に本当に必要な資金がいくらなのかを把握することです。
老後資金で本当に大切な3つのポイント
- 個別事情を重視する:住まいの状況、健康状態、家族構成によって必要額は大きく変わります
- 現実的な収支を把握する:年金収入と実際の生活費から、本当の不足額を計算しましょう
- 自宅資産を有効活用する:持ち家があれば、リースバックで資金調達しながら住み続けることも可能です
統計の平均値より少なくても、焦る必要はありません。特に持ち家をお持ちの方は、セゾンのリースバックを活用することで、住み慣れた我が家にそのまま住みながら、まとまった老後資金を確保できます。
引っ越しの必要もなく、固定資産税などの負担からも解放されるため、多くのシニア世代に選ばれている解決策です。
まずはセゾンファンデックスの無料相談で、「私の場合はいくら資金調達できるのか?」をシミュレーションしてみませんか。数字が見えることで、きっと老後資金への不安も和らぎます。お気軽にご相談ください。